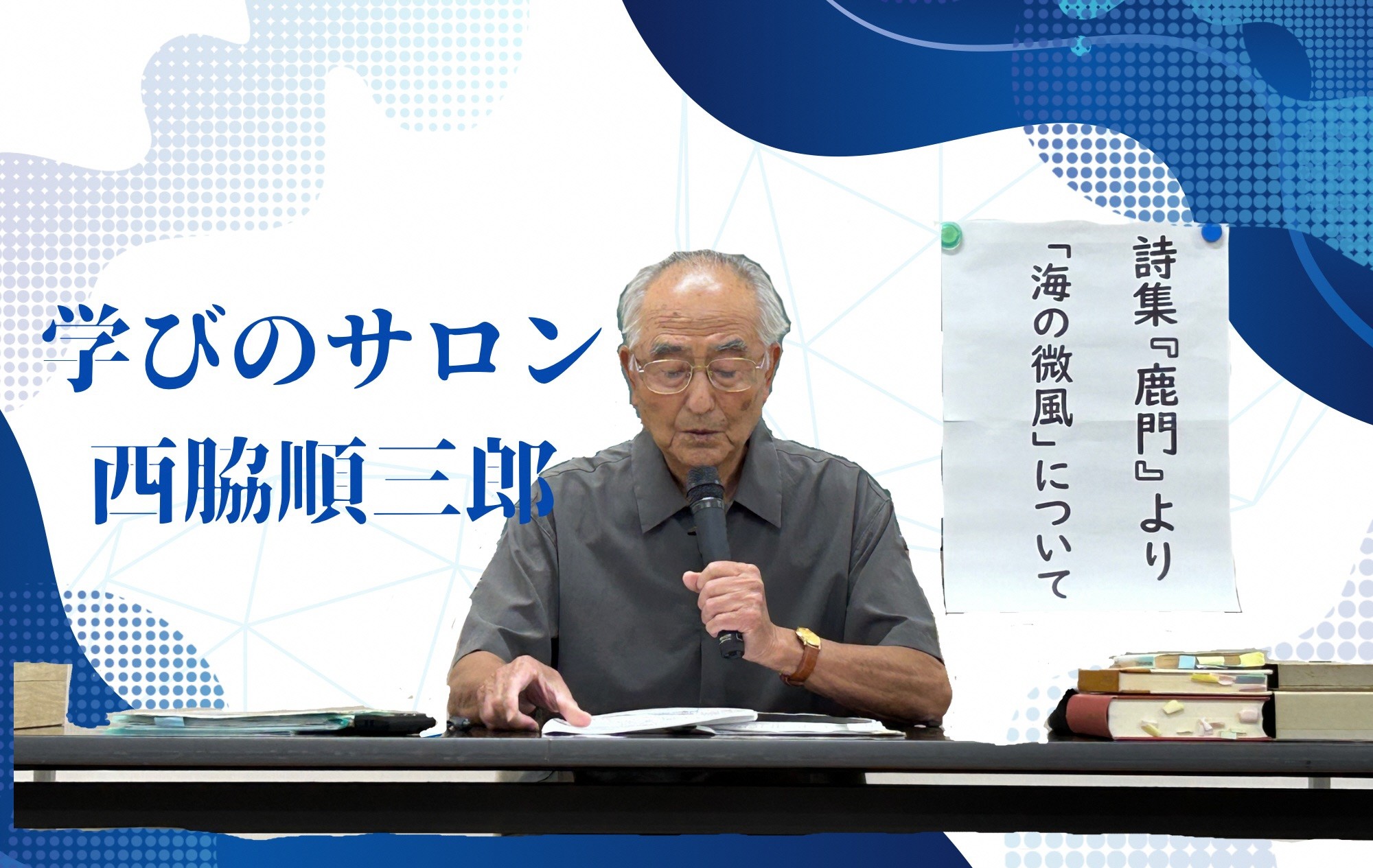
学びのサロン 西脇順三郎_20250705
まなびのさろんにしわきじゅんざぶろうステファヌ・マラルメと西脇順三郎。二人の詩人が「海の微風」というタイトルで詩を残した。 まったく印象が異なるこの二つの詩は、 しかし、マラルメの「海の微風」に西脇の「海の微風」を重ねることで更に受ける印象を変えてゆく――。 西脇順三郎を偲ぶ会が開催する「学びのサロン西脇順三郎」は、西脇順三郎の詩に対してさまざまな切り口から理解を深める講座です。 今年は「私の一押し西脇詩」がテーマとなっており、講師の方が一篇の詩を自身の想いとともに解説する講座を行います。講座は前半・後半の二部構成で前半は聴講、後半が聴講者も参加できるトークセッションの時間になっています。 今年は7月5日、10月13日、11月3日の三回開講される予定で、「私の一押し西脇詩」をナビゲートしてくれる講師の方は毎回変わります。 申込は不要、どなたもお気軽にお越しください。 以下、第1回目となる7月5日の回のハイライトをお届けします。 詳細は2026年発行予定の西脇順三郎を偲ぶ会会報「幻影」をご覧ください。 ■記録:町田
開催概要
日時:2025年7月5日(土) 場所:小千谷市民会館 2階 中会議室 講師:さとう まさお さん 一押し西脇詩:「海の微風」 詩集『鹿門』より
1.はじめに
Q.なぜこの作品を選んだのか? A.以前、新倉俊一先生が小千谷においでになられた時にこういうことを仰いました。「西脇先生のことについてはたくさんの本が出ていたり書かれたりしているけれど、そのほとんどが初期から中期の作品や詩論であります。後期が見過ごされている。大事なことがたくさん書かれているのに」というお話をされていかれました。このことが私の頭にずーっと残っておりました。幸いなことに私の手元に若い頃に買った詩集『鹿門』がありました。この中で私の目をひいたのが、この「海の微風」でした。最終行「おばあさんがせきをした/ゴッホ」という最後の2行がありますが、このゴッホにびっくりして。こんなのが詩になるのか!と思って、それでこの作品に興味が湧いたのであります。
2.作品の成り立ち
作品の底辺をなす詩法などについて (1)イロニイ ・西脇順三郎「二つの相反するものが連結されて融合する一つの存在を意味しています。そしてそれを芸術と呼んで、超自然の美とか真的美をイメージするのであります」 ・ボードレール「イロニイがなければ芸術は存在しない」 (2)パロディ 他人の詩や文章を面白おかしく引用、模倣したりすること。 マラルメの「海の微風」を踏み台にしながら、イメージや言葉を反転させて、自分の作品として組み立てている。 ・マラルメの「海の微風」を読んでみよう →若い男性、生への絶望から嵐の海に沈む… ・西脇順三郎の「海の微風」を読んでみよう →おばあさん、老いや死を受け入れた姿勢、微笑み… (3)この作品には芭蕉が隠されている――? 「地上のさまよいは止めるな」は旅に生涯を送った芭蕉への想い? 「蒼白なアジ」と芭蕉の句のつながり。死のメタファー? 印象的な最後の2行は「古池やかはず飛びこむ水の音」と重なるのではないか? 古池=無音・時間もない・永遠 水の音=瞬間 古池と水の音はイロニーの関係にあり、つまり瞬間が永遠に吸い込まれている。 おばあさんの瞬間を示す「ゴッホ」=永遠へと旅立った瞬間ととることもできるのでは。 昔、講師が西脇順三郎の散歩のお伴をした時に「上代の柿本人麻呂、近世の松尾芭蕉、現在の西脇順三郎」と呟いたのをきいた。あれはご自分の芸術、詩に対する態度・考え方が彼らと同じ流れを汲んでいるという意味で呟かれたのではないか。
3.詩に何を求め、詩作に励んだのか
「海の微風」にそのヒントがみえるのではないか。 【西脇順三郎の人間観】 ・生活の宿命として、生きるために権力や栄達や利得のために争っている。その状態は「人間の自然」であり、現実である。 ・人間の生命は永遠ではない。これは人間の重大な現実。 ・これらの宿命に対して人間は意識的にも無意識的にも憂愁と哀愁を感じている。 「海の微風」後半は、このかなしみを乗り越えるための西脇の考えが出ている箇所。 ・「人間は何かのほとりにいなければならない」:信仰・芸術・趣味など ・「太陽のめぐりを回転しなければならない」:宇宙の法則、永遠に想いを馳せよ ・「玉杯や瑪瑙の指輪を作らなければならない」:芸術(詩)の中に真の美を求めて創作しなければならない。 ↑ ここに西脇順三郎の超自然主義の主張が込められている。 「芸術美はそうした人間の物欲の世界に対抗するために、多くの人の欲求から生まれてきたものでありましょう。それは人間の根本的なヒューマニズムでありましょう」(先達のボードレール・陶淵明・芭蕉らに通底する芸術観)
4.美は「曲がり」にあり
(1)「西脇順三郎の絵画/西脇順三郎と絵画」講師:田野倉康一 西脇順三郎を偲ぶ会記念講演会 2025年6月7日 ⇒西脇の絵画を観ていくと、最晩年の作品は曲線であふれている。山脈や集まった女性(ヌード)の姿を曲線で描く。 (2)蘇った詩人の言葉 講師がかつて雪峠を西脇順三郎と散歩した時に聞いた言葉 「御覧なさい、信濃川ですよ、美しいですね、曲がっているでしょう、曲がっているからこそ美しいのです、美しいものはみな曲がっているのですよ、女性のからだの線もそうでしょ」 (3)良寛の字名 良寛は幼名を栄蔵、長じて字を「曲」(まがり)といった。老子の「曲全」という教えからだが、これもまた競争や争いを原理とする人間の欲の世界に背を向けた芭蕉にも通じるものが感じられる。
5.「海の微風」創作のモチーフ(動機)はいったい何だったのか?
・マラルメの「海の微風」:時間にかかわる言葉は見られない。 ・西脇順三郎の「海の微風」:〝時間〟〝時刻〟〝永劫〟など時間にかかわる言葉が度々使われる。 時間=個々の人間に与えられたもの 時刻=生の始まり、終わりを明示するもの 永劫=果てしない時間のこと 時間、時刻⇔永劫 つまり、イロニーの関係にある。 この二つの概念を連結・融合させながら、永遠と呼ばれる世界への想いを一篇の詩に表現しようと思ったのではないか。 ⇒「永遠」と呼ばれる世界が、この作品のモチーフだった
6.むすびに
「風」には「教え」という意味があるそうです。 西脇順三郎の「超自然主義」という芸術観には二つの面があるんだということを知りました。 一つは芸術としての真の美を求めようとする詩論としての面。 そして二つ目は競争や争いが当然となっている人間の自然世界に抵抗して、素朴な野原の自然に親しむ生き方を示す人生観としての面。その二つがこの「超自然主義」という考え方にあるということを、今回、改めて教えられた気がします。
■ここからはセッションタイムで出た意見や感想
参加者 「西脇順三郎は自分の経験を詩にするので、実際に海辺に行った時のことを思い出しながら書いたのだろうと思う。冗談やユーモアがある詩で難しいと同時に楽しみながら読んだ。今日の講師の話を聞いて、深く読むこともまた楽しいと感じた」 司会者 「最初に読んだ時には難しいが大したことのない詩だと思った。フランス語でマラルメの「海の微風」を読み、この詩の本当の意味がわかるな、と感じた。やはり西脇順三郎の「海の微風」はマラルメの「海の微風」を下敷きにして書いていると思う」 参加者 「メメント・モリの詩だと思った。講師が二時三分を老女の死亡時刻ととらえたが、そのような見方もなるほどと思えて面白かった」 講師 「時間を数えよという文言から刻々と与えられた時間が経過していく。メメント・モリ、この作品のテーマが限りある時間・死であることを示す文言だと思う」 司会者 「自分は詩の後半の時間のくだりやおばあさんの咳についてそこまで深読みしなくてもいいのではと思う。軽い意味、パロディ。砂浜でゆったり過ごそうと思ったのに茶店にいったら次々色んな人が現れて台無しになった、という詩なのではないか」 参加者 「村の校長がくねくねやって来て、というくだりがあるが、これはなんなんでしょうね?」 講師 「これもまたクネクネなので、曲がっていますよね。やはり良いひと、なのでは」 参加者 「この詩はくねくねとやって来る村の校長も含めて茶店に人がどんどん来る。それによってコミカルさが出ていて非常に面白みがあると思う」 参加者 「二人の詩を並べると詩の造形が一目瞭然になると思った。以前に小林秀雄が『実朝』の文章の中で、実朝のうたを解釈するのではなく、姿形とただ向き合う、と言っているが、この二人の詩のエッセンスもそうしてみると同じだと思う。三、四行詩になるのではないか。「時間を数えよ」「時間は一時になろうとしている」「時間はもう一時半になった」「ちょうど二時三分に」この四行に収まるのではないか。マラルメに出てくる「難破船」、西脇の「地平の攪乱」も人生そのものを暗喩していると思うが、そういったものが海の底に沈み、時間と共に海の上を微風が吹いている。そこに西脇とマラルメに共通するエッセンスがあると思う。「二時三分」と具体的な時刻が出てくるが、自分は臨終の時を医師が宣言するところを思い浮かべた。人の持つ時間=命の象徴だと思う」 講師 「今の話を聞いてかつて詩人との散歩のお伴をした時に実朝の話をされていたのを思い出した。いずれにせよ、この詩はものすごく豊富なイメージに溢れかえっていると言える」 参加者 「西脇順三郎の詩を本気で読んだことはなかった。このような形で抽出されたような詩に触れることはあるが、西脇順三郎の詩の全容というのはやはり掴めない。自分にはまだこれは良いな!これはわかる!という詩はありません」
講師が最も参考にした文献
- 「わたしの詩論」(『西脇順三郎研究資料集 第4巻』澤正弘/編集、クロスカルチャー出版、2015年)
- 「芭蕉の精神」(『あざみの衣』西脇順三郎/著、講談社、1991年)
場所
今年度の「学びのサロン西脇順三郎」の会場はいずれも小千谷市民会館 2階 中会議室です。
- 名称
- 小千谷市民会館
- よみがな
- おぢやしみんかいかん
- 住所・場所
- 〒947-0031 新潟県小千谷市土川1丁目3−3
問い合わせ先
- 名前
- 西脇順三郎を偲ぶ会事務局
- 電話番号
- 0258-82-2724